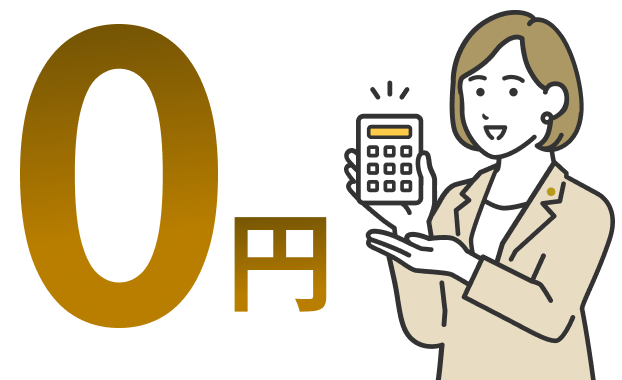相続人が遺産分割協議に応じない! 遺産分割協議を進めるための方法
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議
- 応じない

日本全国には、何代にもわたって相続の手続が行われないまま放置されて、誰が所有者なのか分からない土地が点在しており、その面積は九州本土よりも広いといわれています。
相続人になられた方は、必要な相続手続を行わなければ不利益を受ける可能性もあることに注意が必要です。また、相続手続の中で最も手間がかかるのは、原則として相続人全員が参加しなければならない遺産分割協議となりますが、遺産分割協議に応じない相続人がいる場合には相続手続が進められず立ち往生してしまうこともあります。
本コラムでは、一部の相続人が遺産分割協議に応じない場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説します。


1、遺産分割協議とは?
遺産分割協議は、遺言がなく、相続人が複数人いる場合に、「誰がどの遺産を相続するのか」を相続人どうしの話し合いによって決める手続です。
まずは、遺産分割協議の方法などについて解説します。
-
(1)遺産分割協議の方法
遺産分割協議は、相続人全員が参加して話し合いを行い、最終的に全員が遺産の分割方法について合意することにより成立します。
協議自体は必ずしも相続人が一度に集まって話し合いをする必要はなく、メールやSNS、電話などの方法でも問題ありません。
なお、遺産分割協議を行う前提として、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて「誰が相続人なのか」を調査する必要があります。
また、遺産分割協議が成立した際には、その合意内容を記した遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
これらの書類は、不動産の相続登記や預貯金の解約など、遺産の名義を相続人に変更する際に必要となります。正しいやり方で書類を用意しないと、名義を変更する手続が上手く行かないこともありますので、ご注意ください。 -
(2)遺産分割協議はいつまでにすればいい?
遺産分割そのものには、期限はありません。
しかし、民法では遺産分割で考慮される事情として、「特別受益」と「寄与分」という制度を設けており、これらの権利を主張することができる期間が相続開始の日から10年間に制限されることになりました(令和5年(2023年)4月施行)。
特別受益とは、被相続人の生前に住居や学資などの贈与を受けた相続人がいる場合に、その贈与分は遺産分割において取得したものとみなして、他の相続人との公平を図る制度です。
また、寄与分とは、被相続人の財産の増加や維持に貢献した相続人がいる場合、その寄与した分を相続分に上乗せする制度です。
これらの権利が主張できなくなると、遺産分割は法定相続分で機械的に行うほかなく、実情に合った公平な遺産分割ができなくなる可能性があります。 -
(3)一部の相続人を除いて遺産分割協議をするとどうなる?
相続人が一人でも欠けた状態で遺産分割協議をしても法的には無効です。
相続人全員が署名や押印をしていない遺産分割協議書では、相続登記手続や預貯金の解約ができないため、結局、遺産分割協議をやり直すことになってしまいます。
2、遺産分割協議を行わないとどうなる?
遺産分割協議に応じない相続人がいると、相続の手続を進めることができません。
以下では、遺産分割協議を行わずに相続手続を放置するとどうなるのかについて解説します。
-
(1)相続に関する各種の期限
相続の手続のなかには、相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)を起点として期限が定められているものがあります。
期限がある相続手続のうち、遺産分割協議を行っていない場合に注意が必要な事項は下記の通りです。
① 借金を相続したくない場合の相続放棄・限定承認(3か月以内)
相続人は被相続人が残した財産だけではなく、借金やローンなどの債務も相続します。
借金などの金額が大きい場合は、相続放棄や限定承認をして借金の相続を免れることも選択肢となりますが、これらの手続は原則として相続があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があるのです。
遺産分割に応じない相続人がいる場合でも、相続財産や相続債務の調査を行って、期限までに相続するか否かを判断しなければなりません。
② 相続税の申告・納税の期限(10か月以内)
相続税が課税される場合は相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をする必要があります。
遺産分割協議を行っていない状態でも申告と納税は必要です。
また、小規模宅地等の特例や配偶者控除を受ける場合は、期限内に申告する必要があります。
③ 不動産を相続した場合の相続登記などの期限(3年以内)
不動産を相続した場合は、相続登記など必要な登記手続が義務化される制度が令和6年(2024年)4月よりスタートします。
相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に必要な登記手続をする必要があり、これを怠ると10万円以下の過料の制裁を受けることがあります。
この規定は令和6年4月以前に発生した相続にも適用されるので注意が必要です。 -
(2)遺産分割協議を行わないことによるデメリット
相続の手続に関する期限のほかにも、遺産分割協議を行わないと下記のようなデメリットが発生します。
① 預貯金や不動産などを活用することができない
遺産分割協議をしていない状態では、不動産や株式を売却して現金化したり、預貯金を解約して払い戻しを受けたりするためには、その都度相続人間での意思統一が必要になります。
なお、遺産分割されていない預貯金については、金融機関ごとに最大150万円の仮払いを受けられる制度が令和元年(2019年)7月からスタートしています。
当面の生活資金や相続税の納税資金の工面に利用することも考えられますが、預貯金全額の払い戻しを受けられるわけではないため、遺産分割を行ったほうがいいことに変わりはありません。
② 空き家の管理コストがかかる
遺産のなかに誰も居住する予定がない住宅がある場合、空き家のまま放置されるケースが増えており、「空き家問題」の原因として指摘されています。
適切な管理がされないまま放置された空き家は、倒壊の危険や景観の悪化、犯罪への悪用などのおそれがあり、近隣住民にとって多大な迷惑をかけてしまいます。
そのため、空き家問題に対処する目的で「空き家対策特別措置法」が制定され、空き家の所有者や管理者には、空き家を適切に管理する義務が課せられているのです。
適切に管理されていない空き家は「特定空き家」に指定されて、役所から空き家の管理について助言や指導、勧告、命令を受けることがあり、下記のような不利益を受ける可能性もあることに注意が必要です。- 勧告を受けた場合は固定資産税・都市計画税の負担が重くなる
- 命令に従わない場合は50万円以下の過料に処せられる
- 空き家の取り壊し費用の負担を命じられる
③ 相続財産の散逸・使い込みなどのリスクがある
遺産を放置していると、遺産を勝手に処分されたり、所在が分からなくなったりすることが起こりやすくなります。
また、遺産に関する記憶も曖昧になり、相続人どうしが疑心暗鬼になって、ますます遺産分割協議が困難になるというおそれもあるのです。
④ 数次相続により相続手続が煩雑になることも
遺産分割が終わっていない状態が長く続くと、高齢の相続人が亡くなる可能性もあります。
そうすると、先に亡くなった方の相続(一次相続)と後で亡くなった方の相続(二次相続)が発生することになりますが、この状態を「数次相続」といいます。
数次相続になると、一次相続の相続手続に二次相続の相続人も加わることになり、相続人が増える上に二件分の手続を進めなければならないので、手続がさらに複雑になってしまいます。
3、遺産分割協議に応じない人がいる場合の対処法
遺産分割協議に応じない相続人がいる場合に相続の手続を進めるためには、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用する必要があります。
以下では、家庭裁判所での手続について解説します。
-
(1)申し立ての前に準備するもの
家庭裁判所で遺産分割の手続を行う場合、以下の書類を用意する必要があります。
- 相続関係が明らかになる戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍附票
- 遺産に関する書類(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、有価証券証書の写し、自動車登録事項証明書、査定書など)
-
(2)遺産分割調停
遺産分割調停は、裁判官と民間人から選ばれた調停委員の仲介により遺産分割について話し合う手続です。
相続人全員が調停の当事者となり、全員の合意があれば調停が成立し、合意内容が調停調書に記載されて、不動産の相続登記手続や預貯金の解約などの名義変更手続が可能になります。
また、金銭の支払いや物の引き渡しについて合意したのに相手方が従わない場合は、強制執行をすることもできます。
「遺産分割協議に応じない相続人に調停の申し立てをして意味があるのか?」と疑問に思われるかもしれませんが、裁判所から調停期日への出席を求める書類が届くと、調停には出席したり、意見を記載した書面を提出したりすることもないわけではありません。
調停が不調に終わると、自動的に審判に移行するので、最終的には遺産分割をして相続の手続を進めることが可能になります。 -
(3)遺産分割審判
遺産分割審判は、裁判官が相続人の主張を聴取して事実の調査や証拠調べを行い、遺産分割の方法を決定する手続です。
遺産分割調停ではなく、いきなり遺産分割審判の申し立てをすることもできますが、話し合いによる解決の可能性がある場合は、先に調停が行われることもあります。
審判では、相続人の主張や裁判所が調査して収集された事実が判断の基礎となりますが、審判に欠席すると、欠席した相続人に有利な事情について取り上げられないまま審理が進行することもあります。
審理が終結すると、「審判」という形で裁判所の判断が示され、審判が確定すると遺産の名義変更手続や強制執行が可能になります。
審判に不服がある相続人は、審判の告知を受けてから2週間以内に高等裁判所へ即時抗告をすることができます。
4、相続の問題を弁護士に相談するメリット
相続の手続に関するお悩みやお困りごとは、弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)相続手続全般にわたってサポートを受けられる
相続の手続は、相続人や遺産の調査、遺産分割協議、遺産の名義変更手続、相続税の申告・納付などやるべきことが多岐にわたり、何から手を付ければいいのか分からないという方も少なからずおられます。
弁護士は相続手続について豊富な知識と経験を持っており、手続の期限を意識しながら必要な手続についてアドバイスすることができます。 -
(2)対応が難しい相続人と交渉してもらえる
遺産分割協議で過大な要求をする相続人や、協議に応じない相続人がいると、相手方を説得する方法も分からないまま、相続の手続が立ち往生してしまうことも珍しくありません。
弁護士に依頼すれば、遺産分割協議で円満に解決するメリットや、調停や審判へ手続が進むほど自由な遺産分割が難しくなることなどを説明しながら、遺産分割協議を成立させやすくなります。 -
(3)家庭裁判所の手続も代理人として委任できる
遺産分割協議による解決が難しい場合でも、家庭裁判所での調停や審判の手続を弁護士に委任することができます。
弁護士に依頼すれば、特別受益や寄与分など主張すべき事情については、調停委員や裁判官に法的に整理して主張することができます。
また、弁護士は必要な資料収集についてもアドバイスすることもできるので、遺産分割を有利に解決しやすくなるでしょう。
お問い合わせください。
5、まとめ
遺産分割協議に応じない相続人がいる場合に、相続の手続を行わずに放置することは避けるべきです。
とくに遺産のなかに不動産がある場合は、必要な登記手続や空き家の適切な管理が義務化されているので注意が必要です。
遺産分割協議を行わずに放置すると、特別受益や寄与分の主張ができなくなり、数次相続により手続が複雑化して、問題を次世代に持ち越すことになってしまいます。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士のほか、グループに税理士や司法書士が在籍しているため、相続全般のトラブルについて対応可能です。
相続手続に関するお悩みやお困りごとは、まずはベリーベスト法律事務所 長崎オフィスまで、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています