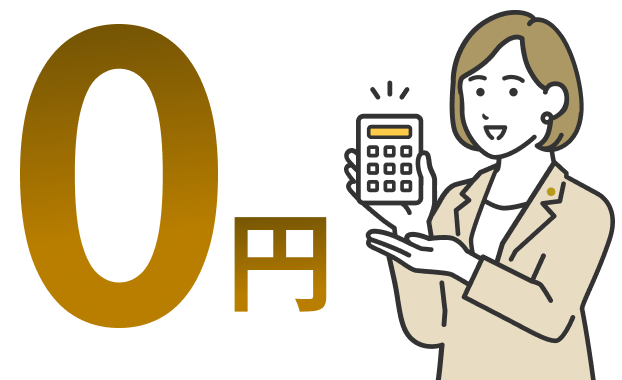遺産相続で妻に全額渡すことはできる? トラブル回避対策と注意点
- 遺産を残す方
- 遺産相続
- 妻に全額

令和2年の厚生労働省の調査によると、長崎県の男女別平均寿命は男性81.01歳、女性87.41歳で、女性の方が男性よりも6.4年寿命が長くなっています。
女性の方が男性よりも長生きすることが多いため、自分の死後は遺産を全額渡して、長年連れ添った妻にはお金の心配をせずに暮らしてもらいたいと考えている方もいるかもしれません。
相続人の状況によっては、妻だけに遺産をすべて相続させることも可能です。しかし、他の相続人にも遺留分という最低限度の遺産相続をする権利が法律上保障されています。また、妻だけに相続するという内容の遺言を作成すると相続争いなどのトラブルが発生する可能性があり注意が必要です。
そこで、できるだけトラブルにならないように妻に遺産を全額渡す方法や相続の際の注意点について、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説します。


1、遺産相続で妻に全額引き継ぐことはできる?
遺産相続で妻に全額を引き継ぐことは可能です。しかし、そのためには条件があります。
-
(1)妻は必ず相続人になる|相続の順序について
民法上、配偶者である妻は必ず相続人になります(民法890条)。他方、配偶者以外にも子どもや父母、兄弟姉妹も相続人に含まれます。ただし、この全員が相続人になるわけではなく、被相続人の子が第1順位、子がいなければ親が第2順位、親もいなければ兄弟姉妹が第3順位となります。
このように、他の親族がいる場合には、配偶者以外にも親族が相続人になることが決められています。
ただし、これらの民法上のルールは、遺言がなかった場合に財産をどのような割合で配分するか決めたものです。「財産のすべてを妻に相続させる」という内容の遺言があった場合には、妻がすべての遺産を受け取る権利があります。遺言は、被相続人の生前の意思を尊重して自由に財産を処分させるための制度であるため、上記の相続の順序に関する決まりに優先して適用されます。 -
(2)妻に遺産を全額引き継ぐことができるケース
以下の3つのケースでは妻が遺産を全額引き継ぐことができる可能性が高いです。
- ① 配偶者以外相続人がいないケース
- ② 遺言があり、他の相続人が兄弟姉妹のみのケース
- ③ 遺言があり、遺留分侵害額請求をされないケース
それぞれのケースについて詳しく説明します。
① 配偶者以外相続人がいないケース
民法上相続の対象となる法定相続人には、一定の割合(法定相続分)での遺産相続が保障されています。「妻にすべての遺産を相続する」という内容の遺言があった場合は、法定相続人に対して、法定相続分の割合ではなく最低限度の遺産相続の割合である「遺留分」が認められます。
「① 配偶者以外相続人がいないケース」では他に相続権を持つ人がいないため、妻に全額相続させることができます。
② 遺言があり、他の相続人が兄弟姉妹のみのケース
また、遺留分が認められるのは、配偶者と子ども(代襲相続人も含む)、父母などの直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、妻と兄弟姉妹しか相続人がいない場合は、妻が全額を受け取ることが可能です。
③ 遺言があり、遺留分侵害額請求をされないケース
また、遺留分があったとしても、その人が「遺留分侵害額請求」をしなければ、財産を受け取ることができません。
よって、「③ 遺言があり、遺留分侵害額請求をされないケース」では妻に全額相続できる可能性があります。
2、遺産相続で妻に全額受け取ってもらうための4つの方法
遺産相続で妻に全額受け取ってもらうためには、生前からしっかり準備をしておくことが大切です。そこで、妻に全額相続してもらうための4つの方法を紹介します。
-
(1)遺言書を作成する
妻に全額受け取ってもらうために、遺言書を作成しましょう。遺言書は、遺言者の意思を尊重し、遺産分割を行う制度です。そのため、自分の死後、誰にどの財産をどの割合で相続したいか、遺言書という明確な形で残しておくことが重要になります。
遺言書を作成するにあたって、遺言書の内容を実行する「遺言執行者」の選任も大切です。遺言書を作成したとしてもその遺言の内容に従って、遺産分割をしてもらうことができなければ意味がありません。そこで、遺言執行者をあらかじめ選任しておき、確実に遺言の内容を実現できるよう準備しておきましょう。
遺言執行者には、相続人以外であれば、親族や友人でもなることができます。ただし、未成年者や破産者を指名することはできないため注意してください。また、親族や友人を選任したとしても、遺言の手続きが複雑だったり、選任した人が高齢になったりして執行が難しくなることもあるかもしれません。
そのようなリスクを避けたい場合は、弁護士や弁護士法人などの組織に依頼するのが得策です。弁護士に依頼をすれば、適切な遺言書の書き方、保管方法などについてもアドバイスをもらうことができるため、一度相談してみるといいでしょう。 -
(2)家族信託を利用する
「家族信託」とは、信頼できる家族に自分の財産を託し、適切な方法で財産の管理・処分を任せる方法です。農地や預貯金口座など一部の財産は信託できないというルールはあるものの、信託契約内容はある程度自由に決めることができるため、自分の意思に沿った柔軟な遺産相続が可能になります。
家族信託には、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という制度があります。この制度は遺言と異なり、自分が亡くなった後の相続人だけでなく、その財産を受け取った次の相続人も指定することが可能です。たとえば、「自分の死後、妻に遺産を相続し、妻の死後は子に遺産を相続する」と指定することができます。
このような家族信託は、先祖代々の土地を有していたり事業を行っていたりする場合に、将来的な相続先を決めることができるというメリットがあります。しかし、信託契約期間の制限や、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があるので注意が必要です。 -
(3)早い段階から生前贈与をする
遺産相続するのを待つだけでなく、自分が生きているうちから妻に財産を渡したい場合には生前贈与するという方法もあります。
生前であれば、他の財産同様、土地や家などの不動産、車などの動産、株式などすべての財産を希望する相手に贈与することができます。年間110万円までの贈与であれば、税金は課されません。
さらに配偶者への贈与の場合、居住している住居や居住するための住宅購入費用は、一定の要件にあてはまれば2000万円まで贈与税が非課税になる配偶者控除制度があります。
贈与税は、相続税より税率が高く、相続開始から7年以内の贈与の場合は相続税だけでなく、贈与税も発生してしまいます。弁護士や税理士に節税対策も含めて、どの財産をどのくらい前にどれだけ渡すのがいいのか相談してみるといいでしょう。 -
(4)他の相続人と事前に話し合っておく
他の相続人と事前に話し合っておくことも、妻に相続財産を全て譲り渡すためには大切なことです。遺産相続の段階になって、妻と親族がトラブルになることは、なんとしても避けたい事態だといえます。子どもなど相続人になる可能性がある親族に自分の意思を伝え、死後は妻に遺産を相続させたいことを相談してみましょう。
3、妻にすべてを相続させたいと考えたときに知っておきたい注意点
妻にすべてを相続させたいと考えたとき、知っておかなければならない注意点があります。妻に全額相続させることがゴールではなく、老後を不安なく穏やかに過ごしてもらいたいと考えるなら、以下についても配慮しておきましょう。
-
(1)遺留分をめぐってトラブルになる可能性がある(遺留分侵害額請求)
妻にすべてを相続するということになれば、他の相続人は不満を持ち、遺留分をめぐってトラブルになる可能性があります。
妻にすべての遺産を相続するという内容の遺言書を残したとしても、遺留分の相続権を持つ相続人は、妻に対して、遺留分相当額の金銭を請求できます(遺留分侵害額請求)。請求に対して、素直に応じれば支払いだけで終わりますが、金額に納得できない場合には調停や裁判になる可能性もあります。
遺留分は、相続人に最低限度の財産の相続を認める制度であるため、請求された場合支払う必要があるケースも多いです。事前に他の相続人と話し合うことや、弁護士に相談しておくことがトラブルを回避のためのポイントになります。 -
(2)二次相続で子どもの税負担が大きくなる
妻にすべての財産を相続させると、子どもの税負担が大きくなる可能性があるため、十分な検討が必要です。妻に相続させた財産は、その後基本的に子どもが相続することになります(二次相続)。そのとき、妻に相続させた遺産を相続する子どもに、相続税が生じます。
すなわち、遺産に対して
① 妻に相続したとき
② 子どもが相続するとき
の2回の相続税が発生することになるのです。
一般的に配偶者に相続させたほうが、子どもに相続させるより相続税が安く、節税対策になるといわれることもあります。しかし、自分から子どもに直接相続させた方が相続税の支払いが1回で済むので、長い目で見たら得になるかもしれません。
たとえば、「配偶者居住権」を設定すれば、自宅と土地の所有権を子どもに相続させても、妻に居住権を相続させることで、妻が亡くなるまで自宅に住み続けることができます。
うまく制度を活用し、二次相続も含めどのように相続することが得策か考えるようにしましょう。
参考:「配偶者居住権とは何ですか?」(ベリーベスト法律事務所) -
(3)妻が認知症になっていると遺産分割協議が難航する
相続するころには妻も高齢になり、認知症になっているということも想定しておかなければなりません。認知症になってしまうと、遺産分割協議が難航する可能性があります。認知症の人は、判断能力が低下し、法律的な意思表示が難しい状態であると判断されるので、相続人全員で行わなければならない遺産分割協議に意思表示ができない人がいると遺産分割が難しくなってしまいます。
認知症の人がいる場合には、成年後見制度を利用し、その人の代わりにその人のために財産の管理や法律的な意思表示をする成年後見人を選ばなくてはなりません。遺産分割協議だけでなく、成年後見制度の手続きも発生するため、協議が長引くことが考えられます。
こういったもしもの状態を想定し、事前に他の相続人と話し合っておくことも重要です。 -
(4)不動産の処分が遅れる
妻に遺産をすべて相続すると不動産の処分が遅れる可能性があります。たとえば、妻に相続させるつもりで遺言書を残したとしても他の相続人が納得せず、いつまでも遺産分割協議が終わらないケースです。
このような場合、遺産分割協議が終わるまで不動産などの財産に手をつけることができないため、売却したいと思っても売ることはできません。資産を売って今後の生活費にしてほしいと考え、遺言で相続させるつもりだったのに、うまくいかないということも考えられます。
4、遺産相続に関する悩みを弁護士に相談・依頼するメリット
遺言を作成したり、親族としっかり話し合ったりすることで円滑に遺産相続ができるケースもあります。しかし、遺言書の正しい書き方をはじめ、遺産相続には複雑な法律の知識が必要になる場面も多く、一人で対応するのは大変です。そこで、遺産相続に関する悩みを弁護士に相談・依頼するメリットをご紹介します。
-
(1)トラブルを見越した対策ができる
弁護士に相談することでトラブルを見越した対策をすることができます。たとえば、妻に相続財産のすべてを渡したいとき、どのような手続きをして、誰に説明しておくことが必要なのかアドバイスをもらえることは心強いサポートになります。
相続問題の解決実績のある弁護士であれば、事前にどのようなトラブルが起こる可能性があるのか、教えてもらうこともできます。予想されるトラブルの防止策を事前に提案してもらうことで早めの対策が可能です。 -
(2)法的に有効な遺言作成から執行まで依頼ができる
遺言については、法律上厳しいルールが設けられているため、作成者が法律に詳しくない場合、法的に有効な遺言書が作成できるとは限りません。「妻にすべての財産を相続する」と遺言書に明記したにもかかわらず、法的に誤りがある場合は無効になってしまう可能性があります。
弁護士なら、正しい遺言の作成方法だけでなく、遺言執行者として遺言に従って円滑な遺産分割のサポートを行うことができます。 -
(3)相続発生後のトラブルまで対応できる
どれだけ準備をしても相続発生後にトラブルが起きるかもしれません。問題を解決するために、調停や裁判が必要になる可能性もあります。
遺言書の作成であれば行政書士や司法書士に依頼することもできますが、トラブルが起こった場合に対応できるのは弁護士だけです。遺産相続や遺言の相談を弁護士にしておけば、もしトラブルが起こった場合、迅速に対応することができます。
5、まとめ
配偶者である妻は必ず相続人になるため、遺産を受け取ることができます。しかし、妻にすべての遺産を引き継がせたい場合、遺言の作成や他の相続人への説明など事前の準備が不可欠です。また、遺産分割トラブルや二次相続で税金が高くなる可能性もあるため、自分が亡くなった後だけでなく妻が亡くなった後のことも考えて、どういう対応がベストなのか、事前に弁護士に相談してみるといいでしょう。
ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスでは、遺産相続の経験ある弁護士が遺言の作成から遺産相続トラブルの対応まで幅広くサポートいたします。相続や遺言書作成でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|