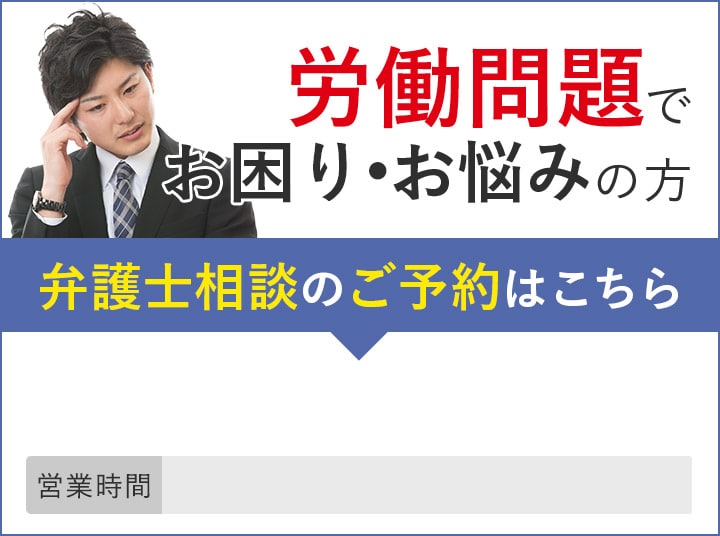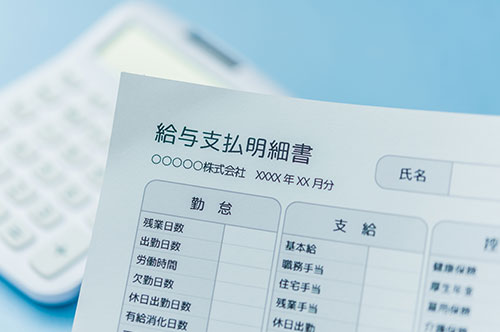【労働者向け】退職勧奨に応じない場合は? 対処法やリスク
- 不当解雇・退職勧奨
- 退職勧奨
- 応じない場合

長崎労働局が発表している「令和5年度長崎労働局管内における個別労働関係紛争解決制度の運用状況及び均等関係法令の施行状況」によると、令和5年の民事上の個別労働関係紛争相談件数は3252件で、前年度と比較して1.0%増加しました。その中でももっとも多かったのが「自己都合退職」の831件と前年度と比較して11.7%増加しています。
会社から「早期退職してくれないか?」「辞めてほしい」などと退職勧奨をされた場合、どうすればよいのかわからず困ってしまうのは当然のことです。退職勧奨に応じない場合にどのようなリスクがあるのかわからず、拒否を示すことに抵抗があるという方もいらっしゃるでしょう。
退職勧奨を拒否することは可能ですが、適切な対応を取らないと、不本意な退職に追い込まれる可能性があります。そこで、退職勧奨を拒否した場合の影響や対処法について、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説します。


1、会社の退職勧奨に応じない場合はどうなる?
会社から退職勧奨を受けた場合、必ず応じなければならないのでしょうか?
そもそも退職勧奨とはどのようなものなのか、応じない場合のリスクについて詳しくみていきましょう。
-
(1)退職勧奨とは何か
「退職勧奨」とは、会社が従業員(労働者)に対して退職を勧める行為のことで、「肩たたき」とも呼ばれています。
退職勧奨は、あくまでも従業員に自主的に退職を勧めるものです。したがって、会社が一方的に労働契約を解除する「解雇」とは異なり、従業員が必ず応じなければならないものではありません。 -
(2)退職勧奨に応じないとどうなるのか
退職勧奨に応じる義務はないため、従業員はこれを拒否することが可能です。「退職してほしい」と会社から言われた場合でも、退職するかしないかは従業員自身が自由に決めることであり、会社が強制することはできません。
また、退職勧奨のやり方が悪質であったり、頻度が多すぎたりする場合は退職勧奨が「退職強要」とみなされる可能性があります。「退職強要」は違法行為となりますので、悪質な場合は損害賠償請求が認められるケースもあります。
退職強要に該当する可能性がある具体的な行為は、以下のとおりです。- 長時間拘束して説得しようとする
- 脅迫して辞めるように迫る
- 従業員が退職勧奨を拒否した後も何度も退職勧奨を行う
- 自分から辞めると言わせるために大幅に仕事量を減らす
2、退職勧奨に応じない場合の対処法
退職勧奨を拒否する際には、適切な対応をとることが重要です。
ここでは、退職勧奨に応じない場合の対処法を4つご紹介します。
-
(1)口頭で明確に伝える
退職勧奨に応じる意思がない場合、明確に「退職には応じません」と伝えることが大切です。言葉を濁したり曖昧な態度をとったりすると、会社側が「交渉の余地がある」と判断し、退職勧奨を続ける可能性があります。はっきりと拒否の姿勢を示すことで、会社が退職勧奨をあきらめることも期待できます。
-
(2)書面で退職勧奨に応じない意思を示す
退職勧奨に応じない場合の2つ目の対処法は、口頭ではなく「書面で退職勧奨に応じないことを示す」という方法です。
口頭で行うよりも書面を送るほうが「退職勧奨を拒否した」という証拠も残るため、後々のトラブル防止にもつながります。
書面は「内容証明郵便」を利用して会社に送付しましょう。内容証明郵便は、送付日や送付内容、差出人や受取人などについて郵便局が証明してくれるサービスです。
これを利用することで、会社に対して退職勧奨拒否の姿勢を示したことを証明することができます。 -
(3)弁護士に相談する
退職勧奨に応じない場合の3つ目の対処法は「弁護士に相談する」という方法です。
退職勧奨が執拗(しつよう)に続く場合や、会社との交渉が難しいと感じる場合、弁護士に依頼すると会社に対して退職勧奨に応じないという内容の書面を送付してもらうことができます。弁護士から書面が送付されてくると、会社は退職勧奨をやめる可能性が高くなるでしょう。
それでも退職勧奨をやめない場合は、弁護士が直接会社と交渉し、状況に応じて損害賠償請求をすることも可能です。 -
(4)裁判所に退職勧奨・退職強要差し止めの仮処分を申し立てる
退職勧奨に応じない場合の4つ目の対処法は、「裁判所に退職勧奨・退職強要差し止めの仮処分を申し立てる」という方法です。
この手続きを行う際には、証拠の確保が重要です。以下のような証拠を準備しておきましょう。- 録音データ(退職勧奨の面談の録音など)
- 書面(会社からの退職勧奨の通知や、退職勧奨を拒否したメールなど)
- メモ・記録(退職勧奨の日時、面談時間、出席者の名前、会社側の発言内容など)
- 診断書(退職勧奨が原因で精神的な負担を受けた場合)
特に、退職勧奨の頻度が多すぎたり、「退職しないと不利益を受ける」などの発言があったりした場合は、違法性が問われる可能性があります。
3、退職勧奨に応じない場合のリスク
退職勧奨は強制ではないため、拒否することが可能です。
しかし、退職勧奨を拒否したことで、会社が何らかの不利益な対応を取る可能性も考えられます。
ここでは、退職勧奨に応じない場合に考えられるリスクをご紹介します。
-
(1)異動を命じられる可能性がある
退職勧奨に応じない場合、会社から異動を命じられる可能性があるでしょう。
会社が業務上に必要な場合に従業員の異動を命じることは違法ではありません。しかし、「退職をさせるため」や「嫌がらせのため」といった不当な理由による異動命令は、人事権の濫用として無効になる場合や損害賠償請求ができる場合もあります。
そのため、退職勧奨を拒否した後に受けた異動命令に納得ができない場合は、一度弁護士に相談してみることもおすすめです。 -
(2)給料を減額される可能性がある
退職勧奨に応じない場合、会社から給料を減額される可能性もあります。給料を減額することで自主的に退職するように会社が圧力をかけてくるのです。
しかし、根拠のない給料の減額は違法であり、根拠があっても会社から一方的に給料が大幅に減額されることは認められません。
退職勧奨を拒否した後に根拠なく給料が減額された場合は、弁護士に相談し、違法性を確認しましょう。 -
(3)解雇を言い渡されるリスクがある
退職勧奨に応じない場合、解雇を言い渡されるリスクがあります。
ただし、解雇には厳しい成立要件があり、簡単に解雇することはできません。
労働契約法第16条(解雇の制限)により、「客観的に合理的な理由がある」「社会通念上相当と認められる場合にあたる」という条件を満たさない解雇は無効とされます。
解雇には大きく分けて以下の3種類の解雇があります。- ① 普通解雇(能力不足や健康状態の悪化を理由とした解雇)
- ② 整理解雇(会社の経営上必要とされる人員削減のための解雇)
- ③ 懲戒解雇(会社の秩序違反に対する制裁として行われる解雇)
しかし、退職勧奨を拒否すると、解雇の成立条件を無視して成績不振を理由に「普通解雇」を言い渡されるケースや、「整理解雇」を言い渡されるケースがあります。なかには「懲戒解雇」という懲戒処分の中でももっとも重い処分を下されることもあるでしょう。
解雇が適法かどうかを判断するためには、「解雇理由証明書」(労働基準法第22条)を請求し、記載内容を確認することが重要です。自分のケースが正当な解雇に該当するかわからない場合は弁護士に相談しましょう。
4、退職トラブルを弁護士に相談すべき3つの理由
退職勧奨を受けた際、自分ひとりで対応すると不利な条件で退職に合意してしまう可能性があります。特に、会社からの圧力が強い場合、退職届にサインしてしまい、後から「本当は辞めたくなかった」と後悔するケースも少なくありません。
弁護士に相談することで、退職勧奨に適切に対処し、法的に有利な立場を守ることができます。ここでは、弁護士に相談すべき3つの理由を解説します。
-
(1)退職勧奨に対する最適な解決策を提示できる
弁護士に相談することで、退職勧奨された場合の最適な解決策を提示してもらうことが可能です。
退職勧奨を受けた場合「拒否するべきか」「退職を受け入れるべきか」を冷静に判断する必要があります。しかし、会社側の説明だけを聞いて決断してしまうと、不利な条件で退職することになりかねません。
それを防ぐためにも弁護士に相談し、最適な解決策を提示してもらいましょう。 -
(2)会社との交渉を代行できる
弁護士に依頼すれば会社との交渉を任せられるというメリットもあります。退職をしたくない場合は退職勧奨をやめるように交渉してもらったり、退職する場合は自分に有利な退職条件になるように交渉してもらったりといったことも可能です。
-
(3)違法な不利益処分や解雇に対処できる
弁護士であれば退職勧奨に応じないことを理由とした不利益処分(違法な減給や異動命令、降格等)や解雇に対処できるというメリットもあります。
弁護士に相談することで会社側の違法性を指摘し、不利益処分の撤回や損害賠償請求を求めることが可能です。
5、まとめ
退職勧奨は解雇とは異なり、応じるかどうかは本人の意思によって決められるため拒否することができます。また、退職勧奨の頻度が多すぎたり悪質だったりした場合は、損害賠償請求を検討することも可能です。
退職勧奨を受けた際に、「応じるべきか拒否するべきか」をひとりで判断するのはリスクがあります。退職勧奨を受け入れたくない場合や、受け入れるか迷っている場合も、早めに弁護士に相談することをおすすめします。その際はぜひ、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています