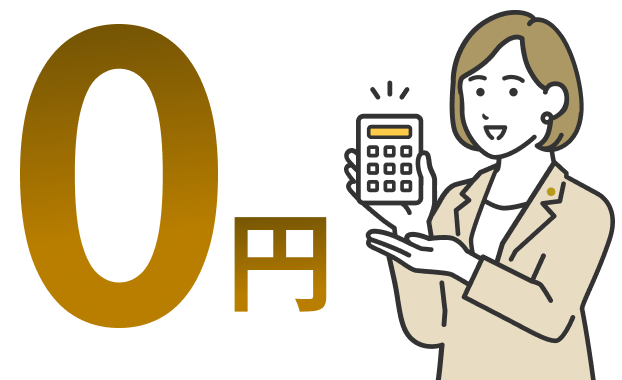不当利得返還請求のやり方とは? 要件や注意点を弁護士が解説
- 遺産を受け取る方
- 不当利得返還請求
- やり方

長崎県が公表している「長崎県異動人口調査 年間集計」によると、令和5年における県内の死亡者数は1万9746人と出生数を上回っており、全体人口は1万1995人減少しています。
親族が亡くなると相続が発生します。しかし、相続のタイミングでさまざまな問題が露呈することも少なくありません。被相続人と同居していた相続人による、相続財産の使い込みも、そのひとつといえるでしょう。
使い込みが発覚した場合には、「不当利得返還請求」という方法で、使い込まれた遺産を取り戻せる可能性があります。ただし、不当利得返還請求をする際には一定の要件を満たす必要があり、請求できる範囲も法律上決められています。
今回は、相続人による遺産の使い込みが判明したときの不当利得返還請求のやり方と注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説します。


1、不当利得返還請求とはどのような手続き?
まずは、不当利得返還請求権とはどのような手続きなのかを説明します。
-
(1)不当利得返還請求とは
不当利得返還請求とは、法律上の原因なく利益を得たときに、それにより損害を受けた人が利益の返還を請求することをいいます。
たとえば、相続人が遺産の使い込みをした場合、使い込んだ人は本来得られるはずのなかった利益を得て、それにより他の相続人に損害を与えています。そのため、遺産の使い込んだ相続人に対し、不当利得返還請求を行うことによって使い込まれた遺産を取り戻すことができます。 -
(2)不当利得返還請求が発生する要件
遺産の使い込みを理由として不当利得返還請求をするには、一定の要件を満たす必要があります。
- ① 遺産の使い込みにより利益が生じていること
遺産の使い込みをした人が、何らかの利益を得ている必要があります。
たとえば、遺産に含まれる現金や預金を自分のものにした場合、「利益を得た」といえるでしょう。
- ② 遺産の使い込みにより損失が生じていること
相続人が遺産に含まれる現金や預貯金を自分のものにした場合、他の相続人は本来もらえるはずだった遺産が減るため、「損失」があったといえます。このように、遺産の使い込みにより具体的な損失が生じたことが必要です。
- ③ 利益と損失との間に因果関係があること
相続人が遺産を使い込んだことで生じた利益と、他の相続人に生じる損失に、因果関係が認められなければいけません。
- ④ 遺産の使い込みに法律上の原因がないこと
遺産の使い込みがあったとしても法律上の原因がある場合には、不当利得返還請求は認められません。法律上の原因とは、「生前贈与があった」などの事情です。
- ① 遺産の使い込みにより利益が生じていること
-
(3)不当利得返還請求で取り戻せる範囲
不当利得返還請求をすることで使い込まれた遺産を取り戻すことできますが、必ずしも全額を取り戻せるとは限りません。
不当利得返還請求で取り戻せる範囲は、基本的には「現存利益」の範囲に限定されています。現存利益とは、遺産を使い込んだ人の手元に現在残っている利益のことです。
たとえば、遺産を使い込んだ人が浪費やギャンブルですべて使ってしまった場合、手元に残った利益はないため返還請求は困難です。他方、生活費として使った場合には、自分の財産の減少を免れているため現存利益が存在します。
ただし、遺産の使い込みをした相続人が不当利得であることを知っている場合には、全額の返還請求が可能です。 -
(4)不当利得返還請求権の時効
不当利得返還請求は、権利行使することなく一定期間経過すると、時効により請求する権利が消滅します。具体的な時効期間は、以下のいずれか早い方のタイミングです。
- 請求できることを知ったときから5年
- 請求できるときから10年
すなわち、遺産の使い込みを知ったときから5年、または遺産の使い込みがあったことを知らなかったとしても遺産の使い込みがあったときから10年で不当利得返還請求権は消滅してしまいます。
そのため、遺産の使い込みが判明したときは、早めに対応するようにしましょう。
2、不当利得返還請求の手続き
遺産の使い込みをした相続人に対して、不当利得返還請求をする際の手続きについて解説します。
-
(1)財産の使い込みによる不当利得に関する証拠を集める
不当利得返還請求をするためには、まずは財産の使い込みに関する証拠が必要です。
たとえば、預金の使い込みであれば、被相続人の預金口座の取引履歴を確認することで、不自然な出金の有無を明らかにすることができるでしょう。
証拠がない状態で相手に請求したとしても、使い込みを否定されてしまうと、追及するのは困難になります。裁判をするにしても、不当利得の返還を請求する側が遺産の使い込みがあったことを立証する必要があるため、証拠は非常に重要です。 -
(2)内容証明郵便を送る
遺産の使い込みに関する十分な証拠が確保できたら、内容証明郵便を利用して不当利得返還請求を行います。
内容証明郵便は、普段利用する郵便とは異なり、差出人や宛先、内容、差出日などの項目を証明できる郵便なので、相手に対してプレッシャーを与えることができます。
また、不当利得返還請求をすることは法律上の「催告」にあたるので、時効の完成を6か月間猶予することができます。内容証明郵便を利用すれば、催告をしたという証拠になります。
そのため、不当利得返還請求をする際には、まずは内容証明郵便を送ることから始めるようにしましょう。 -
(3)相手との話し合いを行う
内容証明郵便が相手に届いた後は、話し合いによる解決を試みます。
相手が遺産の使い込みを認めているのであれば、返還すべき金額や支払い方法などの条件を話し合いましょう。当事者間で合意が成立すれば、合意内容をまとめた合意書を作成し、使い込まれた遺産を返還してもらいます。 -
(4)合意できなければ不当利得返還請求の訴訟を提起する
相手との話し合いで合意に至らないときは交渉を打ち切り、裁判所に不当利得返還請求訴訟の提起をします。
不当利得の返還を命じる判決が確定すれば、強制執行の申し立てを行うことができるので、遺産を使い込んだ人の財産を差し押さえ、使い込まれた遺産を強制的に回収することが可能です。
3、不当利得返還請求を行う場合のポイント
不当利得返還請求は、ポイント押さえて行うことが大切です。
-
(1)使い込みの証拠を集める
遺産の使い込みの事案では、相手に対して不当利得返還請求をしたとしても、素直に応じないケースが多いです。そのような場合には、証拠に基づいて遺産の使い込みがあったことを立証していく必要があるので、事前に十分な証拠を集めることが重要です。
たとえば、遺産の使い込みをした相続人が「このお金は、被相続人からの贈与を受けたお金だ」などと反論された場合は、贈与契約書などの証拠を求めるとよいでしょう。
また、当時の被相続人が認知症であった場合には、被相続人に判断できる能力があったのかが重要になるので、診断書、医療記録、介護記録、要介護認定記録などの証拠を集めるようにしましょう。 -
(2)相手が不当利益と認識していたかを確認する
使い込んだ相手が自分の行為が不当利得だと知らなかった場合は、現在手元に残っている利益(現存利益)の返還のみを請求できます。
一方、相手が自分の行為が不当利得だと知っていた場合は、利益の全額の返還を請求できます。
全額の返還を求めるためには、相手が不当利得であることを知っていたことを証明する必要があります。相手からよくある反論としては、「被相続人から代理権が与えられていると思っていた」、「自分の財産と勘違いしていた」といったものがあります。これらの反論があったときでも、再反論できるよう十分な証拠を集めておきましょう。 -
(3)相続税の申告期限に注意する
遺産の総額が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)を超える場合には、相続税の申告が必要になります。相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内とされているため、期限に間に合うように相続税の申告を行わなければなりません。
遺産の使い込みに関する争いが解決せず、正しい遺産分割ができないという場合でも、期限内の相続税申告は必要です。
その場合は未分割のまま申告し、後から修正申告する方法で対応するとよいでしょう。
4、相続トラブルを弁護士に依頼するメリット
遺産の使い込みなど相続トラブルに関するお悩みは、弁護士に相談することがおすすめです。
-
(1)証拠が適切なものかどうか法的な観点からアドバイスを受けられる
遺産の使い込みに対する不当利得返還請求をする際には、証拠が重要になります。しかし、一般の方では、どのような証拠を集めればよいのか、手元の証拠だけで足りるのかなど判断が難しいこともあります。
弁護士であれば不当利得返還請求に必要となる証拠を熟知しているため、証拠が適切なものであるかどうか法的観点からアドバイスが可能です。また、手元の証拠だけでは不十分だという場合には、証拠収集についてもサポートしてもらえます。 -
(2)遺産の使い込みの調査をしてもらえる
遺産を使い込んだ疑いがあるものの、相手がそれを認めないケースでは、不当利得返還請求の前提として遺産の使い込みの調査を行わなければなりません。
弁護士であれば、弁護士会照会という特別な調査方法により、遺産の使い込みがあった証拠を入手できる可能性があります。遺産の使い込みに関する調査にあたっては、専門的な知識と経験が必要になるため、まずは弁護士に相談するようにしましょう。 -
(3)交渉や訴訟に発展しても対応を任せられる
遺産の使い込みがあった場合、遺産の使い込みをした相続人との交渉により解決を図ることになりますが、親族という身近な関係間でトラブルについて話し合うのは容易ではありません。
弁護士は、ご依頼者の方に代わって相手との交渉を行うことができるため、交渉による負担を大幅に軽減できます。また、交渉が決裂して訴訟に発展したとしても、引き続き対応を任せられるため安心です。
お問い合わせください。
5、まとめ
不当利得返還請求とは、不当に利益を得た相続人などに返還請求をすることです。
得られるはずの財産が使い込まれていた場合、適切な手続きによって取り戻せる可能性があります。ただし、不当利得返還請求には時効や証拠の集め方など、いくつか注意すべきポイントがあるので、適切に不当利得返還請求の手続きを進めていくには、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
不当利得返還請求などの相続トラブルを抱えている場合は、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています